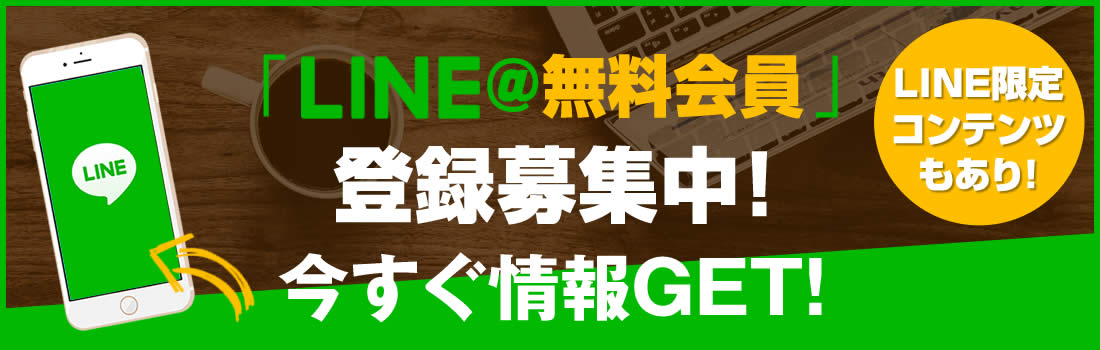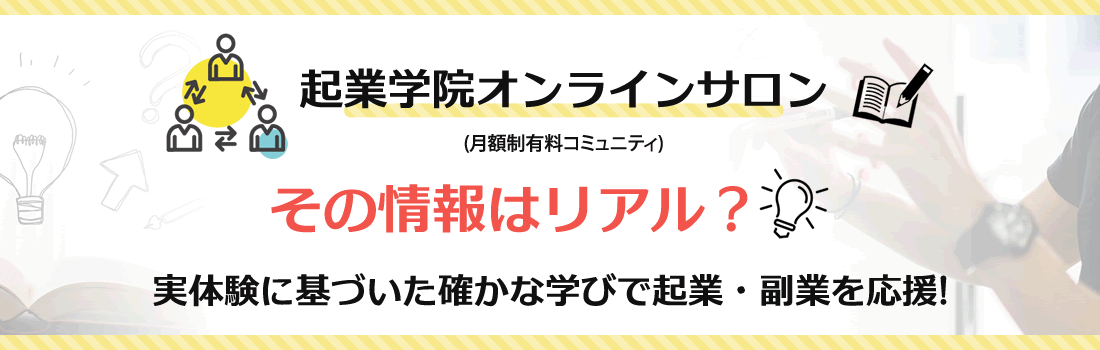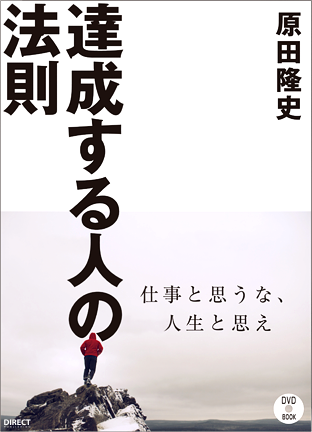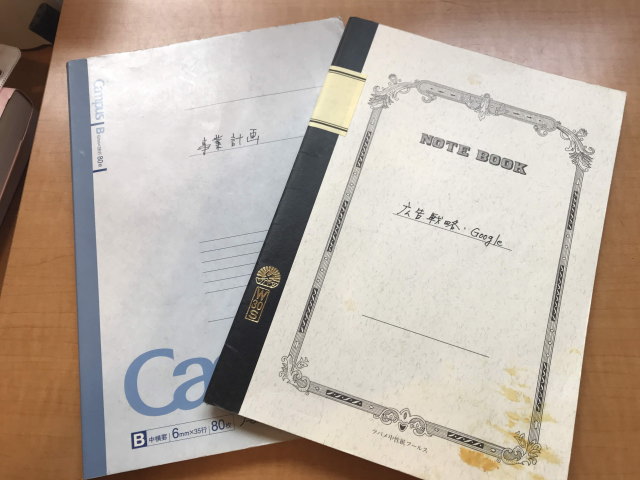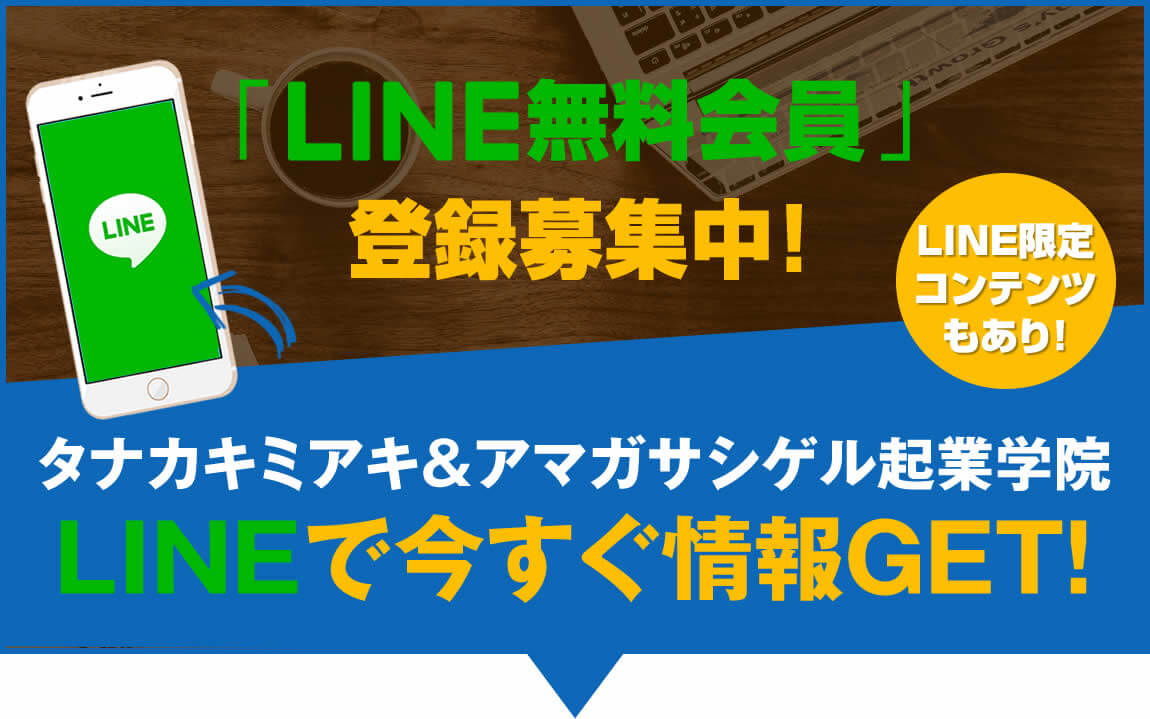個人事業主と法人 どっちで起業するか?どっちが得?

「個人事業主と法人化」について、起業学院スタッフNが調べてみました!最後にアマガサ教頭のコメントもあります。
個人事業主と法人化のメリット・デメリット
起業する際、個人事業主か、法人でスタートするか迷う方は多いと思います。
アマガサ教頭は起業当初から会社を設立したと言ってました。
では、個人事業主と法人化それぞれのメリット・デメリットは何でしょうか?
法人化のメリット
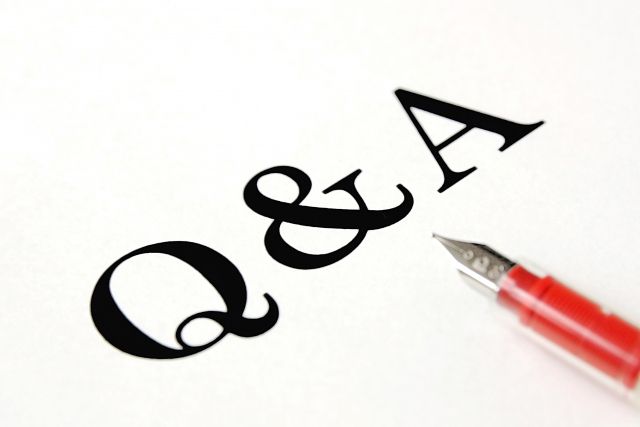
①節税対策
年間の所得が500~600万円を超えると、法人化した方が節税になると言われています。
②経費対策
個人事業主の場合、経費として計上できるのは「その収入を得るための必要経費」と限定されています。
しかし、法人の場合、企業活動において支出するものは経費として計上することができます。
そのため、経費の幅が多く広がり、これもまた大きな節税効果となります。
③有限責任にできる
個人事業主の場合、経営が悪化した際、仕入れ先への未払い金や金融機関などからの借入金は個人の負債として背負うことになります。
一方、法人の場合には、個人保証による借入を除くと出資金の範囲内での責任になります。
④信用度の向上
一般的に個人よりも法人の方が信用度が高く、取引先を法人に限定している企業もあります。
法人化することで取引先を確保しやすくなり、取引先の幅が広がります。
また、金融機関からの借入を行う際にも個人では事業目的の融資は受けにくく、借入できても保証人を求められるケースが多いのが現実です。
法人化することで信用力が上がり、金融機関からの融資など、資金調達がしやすいこともメリットに挙げられます。
⑤社会保険に加入できる
従業員を社会保険に加入させることで、会社が社会保険料の一部を負担することになりますが、優秀な人材を確保しやすくなります。
⑥その他
退職金を支給できるようになったり、決算日を自由に決めることができます。
法人化のデメリット
①赤字でも税金の支払いがある
個人事業主であれば、赤字経営となってしまった場合には所得税や住民税の負担はありません。
しかし、法人の場合の法人住民税は、赤字であっても発生します。
小規模法人の場合で7万円ほどになります。
②社会保険への加入
健康保険や厚生年金は法人化によって加入必須となります。
従業員分の社会保険料の負担もあるため、法人化によって人件費の負担が重くなります。
金額的負担がかなり大きくなるため、注意が必要な項目です。
③設立費用
株式会社を設立するためには、最低でも24万円程度が必要となります。
④会計・事務処理
申告書の様式が煩雑となり、決算業務を自社で間接させることが困難となるため、税理士などの費用がかかります。
複式簿記が必須となり、事務作業が増えます。
⑤交際費の損金が制限される
個人事業の場合、事業に関連性があれば全額、交際費に損金にできます。
しかし、法人の場合、飲食代は50%の費用を損金となり、法人化によって、損金に算入できる交際費が減ります。
スモールビジネスの場合あまり影響が受けないかもしれせん。
※資本金1億円以下の企業は年間800万円までは全額損金に算入が可能です。
このように、個人事業主、法人化には多くのメリット・デメリットがあります。
事業を拡大していくためには、法人化は不可欠であることから、法人化するタイミングを見極める必要があると思います。
事業の状況と合わせて、法人化についても考えてみてください。
起業後、法人化・個人事業主どっちがお得?

教頭のアマガサです。
起業する際、個人事業主で起業するか?法人化して起業するか?
色々考えますねよ?
せっかく起業したのだから、「社長」と呼ばれたい。
そんな気持ちもあるかもしれません。
一体どちらのほうが得なのか?
たくさんの情報がでているので、色々調べてみてください。
ポイントは消費税と社会保険。
預かった消費税を国に収める。
これ、あたりまえですよね?
しかし、「納税義務の免除」という制度があります。
これをしっかり理解しておくことが大切です。
大雑把にいうと、個人事業主で起業して、その後法人化成りするというパターンが一番得になるでしょう。
ただし、税制改革があるので、最新の情報は国税庁等のホームページをご覧くださいね。
社会保険に関しては、会社にとってかなりの負担になります。
サラリーマン時代は会社に当たり前のように負担してもらっていた社会保険。
自分で会社を立ち上げると
「前の会社はこんなに自分のためにお金を負担してくれていたんだ!」
と驚くでしょう!
私の場合、会社を辞め、新たに法人を立ち上げました。
初めて「社長」と呼ばれたとき、なにかこっ恥ずかしかったのを覚えています。
懐かしい思い出です。
【合わせてお読みください】

 お問合せ
お問合せ